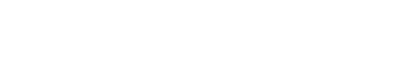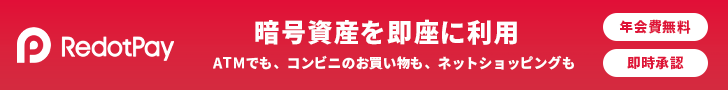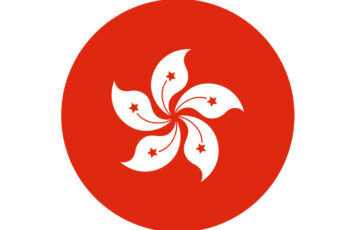SUIとEthenaが共同で新たな安定資産を構築
スイグループホールディングス(SUI Group Holdings)はエセナ(Ethena)およびスイ財団(Sui Foundation)と提携し、Suiブロックチェーン初のネイティブステーブルコイン「suiUSDe」と「USDi」を発表した。
稼働は2025年末を予定。従来USDCに寄っていた流動性を分散し、エコシステムに新たな収益機会をもたらす狙いだ。ナスダック上場のSUIグループが直接関与する点が特徴で、透明性と資本効率を前面に出す。
提携の骨子とコイン設計
suiUSDeはEthenaのプロトコルを活用し、準備資産と先物ショートの組み合わせでドルペッグと利回りを両立させる設計だ。
生じた純収益の一部は市場でのSUI買い戻しに充て、価値の循環をつくる。USDiは、BlackRockのBUIDLマネーマーケットファンドに裏付けられたステーブルコインで、利回りを生まない設計となっており、追加リスクを避けたい利用者に適している。非EVM(イーサリアム仮想マシン)ネットワークとしてネイティブな高利回りステーブルコインをホストするのはSuiが初となる。SUIグループのマリウス・バーネット(Marius Barnett)会長は、両通貨を起点とした「SUIバンク」構想を掲げ、エコシステムの流動性ハブ化を目指す。
The countdown begins for suiUSDe arriving on Sui.
Powered by Sui, @officialSUIG, @ethena_labs, Sui’s first income-generating digital dollar native to a non-EVM chain is coming to Sui ⚡️
Sui and @officialSUIG wil use its revenue to purchase more SUI on the open market. pic.twitter.com/rbrxj5DHnS
— Sui (@SuiNetwork) October 1, 2025
USDC依存を減らす狙い
単一プロバイダーへの依存は、規制や発行体の方針変化に伴うボラティリティや利用制限のリスクを孕む。選択肢を増やすことで、決済やDeFi(分散型金融)での資金調達を柔軟にし、手数料やスプレッドの改善も狙える。
Suiはイーサリアム(Ethereum)やソラナ(Solana)と競合するレイヤー1(L1)として、ステーブルコインの層を厚くすることで差別化を進める。
持続性とリスク、今後の見通し
利回り型のsuiUSDeは普及すれば流動性拡大とSUI需要の押し上げが期待できる一方で、合成型ステーブルコインへの監視強化など規制面の不確実性は残る。
市場需要が弱い局面では再投資モデルのリスクが増す点にも留意が必要だ。SUIグループは準備金収益の活用で財務基盤の強化と株主価値の向上を見込むが、普及の鍵は準備金運用の透明性とオンチェーンでの使い勝手にある。2025年内の稼働に向け、Suiエコシステムでの統合とユースケース拡大が進むかが注目点となる。