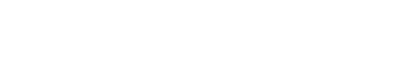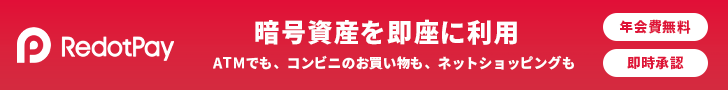ドル主導の市場に対抗し人民元の国際利用を拡大
中国政府が、人民元に裏付けられたステーブルコインの承認を初めて検討していると大手メディアのロイターが報じている。
米ドル建てステーブルコインが世界市場で優位を保つ中、北京は人民元の国際化を進め、ドル依存を和らげる狙いを示す。国務院は今月下旬、導入目標や規制責任の割り当て、リスク管理の枠組みを含むロードマップを審査する予定だ。
人民元ペッグ型のステーブルコインが実現すれば、2021年に仮想通貨の取引やマイニングを禁止した流れから大きな転換となる。計画には、人民元の国際利用に関するベンチマーク設定や、国内規制当局の役割分担、資本フローの監視と国境を越えたコンプライアンスの指針が盛り込まれる。
実行段階は中国人民銀行が中心となり、技術支援とリスク管理を担う見通しだ。上級指導部は人民元の国際化とステーブルコインの活用をテーマに研究会を開き、ビジネスでの利用範囲について公式見解を示す予定とされる。
展開拠点と外交日程
人民元建てステーブルコインの導入は、国内の主要都市と国際会議の双方で進展が見込まれている。
香港
香港ではステーブルコイン関連条例が8月1日に施行され、法定通貨に裏付けられた発行体に対する明確な規則が整った。中国人民銀行の黄一平顧問は、オフショア人民元ステーブルコインの発行は可能性の一つと述べている。
上海
上海はデジタル人民元の国際ハブ構想を進め、地方政府はステーブルコインを含むデジタル資産の扱いを協議している。計画が前進すれば、香港と上海が新制度の実験場として機能する。
天津のSCO首脳会議
8月31日から9月1日に天津で開かれるSCO(Shanghai Cooperation Organisation:上海協力機構)首脳会議では、人民元建て決済とステーブルコインの活用が主要議題となる見通しだ。中国はこの場で、加盟国と人民元建て決済の受け入れやステーブルコインの運用について協議を始める可能性がある。
ドル依存の現実と人民元の課題
米ドル建てステーブルコインは世界の供給量の大半を占め、BIS(国際決済銀行)はそのシェアが九割超であるとする。
テザー(Tether/USDT)やUSDコイン(USDCoin/USDC)は仮想通貨取引の基盤として定着し、国際決済にも浸透しつつある。中国の輸出業者による利用が広がる中、人民元の国際化を損なう要因として警戒が強まった。
SWIFT(国際銀行間通信協会)の統計では、6月の国際決済に占める人民元の比率は2.88%に低下し、米ドルは約47%を維持した。デジタル人民元(e-CNY)はAlipay(支付宝:アリペイ)やWeChat Pay(微信支付:ウィーチャットペイ)の存在感に押され、国内での利用拡大にも課題が残る。
市場動向も追い風と逆風が交錯する。ステーブルコインの世界市場は約2,470億ドル規模とされ、拡大が続く。米国ではGENIUS法に基づき銀行発行のドル担保型を制度化する動きが進め、主要行の予測では2028年までに市場規模が2兆ドル(約297.4兆円)に達する見通しも示されている。中国は資本勘定を全面開放せずに人民元の国際利用を広げたい思惑があり、その実現には厳格な資本規制と市場の利便性の折り合いをつける設計が欠かせない。
人民元建てステーブルコインの承認は、仮想通貨に対する厳しい姿勢を続けてきた中国にとって制度面の大きな一歩になる。ロードマップの具体化、香港と上海での実装、SCOでの合意形成の進み方次第で、人民元の国際利用とドル依存の度合いに変化が生じる可能性がある。まずは今月下旬の審査と首脳会議での議論が、方向性を測る初期シグナルとなる。