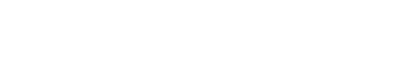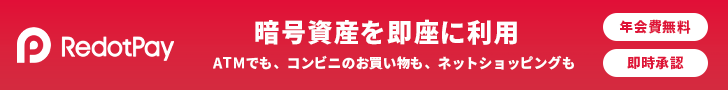米国司法省が仮想通貨犯罪取り締まり部門を解散
DOJ(米国司法省)は、仮想通貨関連の犯罪捜査を専門に扱ってきた「NCET(National Cryptocurrency Enforcement Team:国家仮想通貨執行チーム)」を解散する方針を明らかにした。
2025年4月8日(火曜日)、複数の米国報道機関が報じたところによると、同チームの業務はより広範なサイバー犯罪対策部門に統合される見通しだ。この決定は、米国の仮想通貨規制に対する政府の方針が大きく転換しつつあることを象徴しており、業界関係者の間でも波紋を呼んでいる。
NCETは2021年10月に創設が発表され、2022年2月に正式に業務を開始。仮想通貨を悪用したマネーロンダリング(資金洗浄)やランサムウェア攻撃、サイバー犯罪に対応するための専門部隊として機能してきた。設立当初から、国際的な法執行機関や規制当局と連携。香港に拠点を置いていた仮想通貨取引所で、当時、世界最大規模のダークネットであったHydra Marketとの7億ドル(※現在レートで1,017億円)の取引やランサムウェアから1,500万ドルを(※現在レートで21.8億円)受け取ったことなどで摘発されたビッツラート(Bitzlato)の摘発などで主導的な役割を果たしてきたことで知られる。
このチームは、ウン・ヤング・チョイ(Eun Young Choi)氏が初代ディレクターを務め、仮想通貨関連の金融犯罪への法的対応を牽引してきた。同チームは、司法省刑事局CCIPS(コンピューター犯罪・知的財産部門)に所属する検察官らを含む構成で機能していたが、近年は仮想通貨関連の執行部門の構造や役割に対して見直しの動きがあり、今回の統合は体制の再編成として位置付けられている。
今回の再編は、仮想通貨犯罪をより広範なサイバー犯罪の一部として扱うことで、執行体制の効率化と統合的な対策を進める意図があるとされている。
規制環境の変化と業界の反応
今回の動きは仮想通貨業界全体の監視体制が変化しつつあることを示唆しており、規制アプローチの再評価につながる可能性がある。
トランプ政権下で、仮想通貨に対する規制アプローチの見直しや執行体制の再構築が進められているとの指摘もあり、一部の業界関係者は「規制の一貫性が損なわれる懸念がある」と警鐘を鳴らす一方、過度な監視からの解放として歓迎する声もある。仮想通貨企業にとっては、今後の執行の透明性や予測可能性が新たな注目点となりそうだ。
また、今回の方針転換を司法省がより広範なサイバーセキュリティ問題への対策を優先している兆候として捉えており、仮想通貨関連の案件はその中の一部として位置付けられる可能性がある。
今後の焦点は「誰がどう執行するか」
NCETの解体後、その機能がどこまで保持・拡張されるのかは不透明だ。
DOJのサイバー犯罪対策部門への統合によって、仮想通貨関連の取り締まりが他のサイバー犯罪と同列に扱われる可能性があり、専門性の確保が課題となる。
今後は、SEC(米国証券取引委員会)やCFTC(米国商品先物取引委員会)といった他の規制当局が果たす役割もより大きくなることが予想される。また、複数機関による連携的なアプローチが標準化される可能性もあると指摘されている。米国における仮想通貨規制の枠組みは、司法省単独ではなく複数の機関が連携する形へと移行しつつあり、この変化が、業界の健全な成長を促すのか、それとも混乱を招くのか——その行方が注目される。