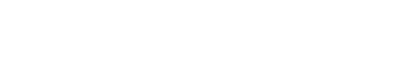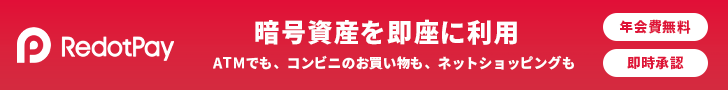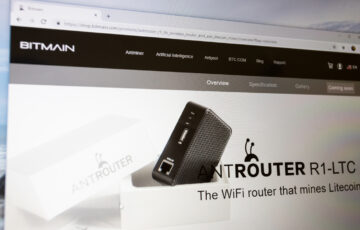国際決済インフラを巡る議論の激化
国際決済ネットワークを担うSWIFTの幹部が、リップル(Ripple)社のXRPを国際送金のブリッジ通貨として用いる提案に疑義を呈し、支持層との論戦が活発化している。
銀行は独自の決済システムやトークン化された預金、規制対象のステーブルコインを選好し、XRPに決済の確定性を委ねる公算は小さいとの見解である。一方、Rippleは低コストと即時性を武器に既存レールの非効率を解消できると主張する。
SWIFT側の主張と銀行の選好
SWIFTのトム・シャッハ(Tom Zschach)CIO(最高イノベーション責任者)は、銀行がXRPのような外部資産に「決済のファイナリティ」を外注するとは考えにくいと述べた。
XRPは預金でも規制対象通貨でもなく、銀行のバランスシートに計上されない点を挙げ、金融機関は自社の内部決済システム、トークン化された預金、あるいは規制されたステーブルコインに依拠する可能性が高いと指摘した。流動性は重要であるが、法的執行力は別の問題であるという立場である。
SWIFTはISO 20022に準拠したブロックチェーンのテストを進めつつも、中核はメッセージングにあり、完全な分散化とは性質が異なる。銀行が最終確定を外部の仮想通貨に委ねることには制度面のハードルが残るという視点である。
Ripple側の反論とXRPの優位点
リップル支持者は、XRPLが決済レイヤーとして機能し、XRPが法定通貨とステーブルコイン間の中立的な流動性ブリッジになり得ると主張する。
XRPは1秒あたり約1,500件の取引を処理し、手数料は約0.0002ドルとされる。従来の国際送金で発生する26~50ドル(約3,800円~7,370円)規模の手数料と比較してコスト優位があるという見立てである。さらに、ノストロ・ボストロ口座(※銀行間の仮想通貨決済で利用される口座)への事前入金で固定化された流動性を、即時変換により解放できる点を強調する。
🚨 XRP haters are celebrating the SWIFT CIO’s comments like it’s the end of the road for XRP…
Tom Zschach (Chief Innovation Officer at SWIFT) argued banks won’t use XRP because they’ll prefer their own rails, tokenized deposits, or regulated stablecoins.
Here’s why he’s wrong… pic.twitter.com/kfMLgUWSBU
— $589 (@589CTO) September 4, 2025
体制整備とプロダクト展開
リップルは、オンデマンド流動性(ODL)の拡大を進め、複数法域でライセンス取得を進展させてきたと示す。
新たに提示されたRLUSDステーブルコインもコンプライアンス重視の一環である。すでに300以上の銀行や決済事業者がXRPLを業務に取り入れており、オンチェーン全体の取引量は1日100億ドルを超えることも珍しくなく、XRPの存在感を際立たせている。
焦点となるのはシェア争いの現実解
SWIFT陣営は、銀行が規制に裏打ちされた枠組みを志向するという現実に立脚し、XRPへの確定性の外注を否定的にみる。
対してリップルは、24時間365日稼働し外部依存の少ない決済レイヤーによりコストと時間を最小化できるとする。2030年までに年間取引量155兆ドル(約2京2,854兆円)規模の14%を獲得する目標が示されており、別の見立てでは5年後にSWIFTシェア15%を獲得するとの予測もある。
今後の見通し
規制の明確化と実運用での信頼積み上げが、どちらの主張を裏付けるかを左右する。
XRPが高ボリューム取引でも確実な決済を継続的に示せるか、あるいは銀行側がトークン化された預金や規制済みステーブルコインで互換性を高めつつ現在の枠組みを強化するか。国際決済インフラを巡る主導権争いは、採用の現場と法制度の整備の両輪で決着していくとみられる。