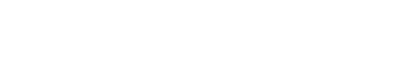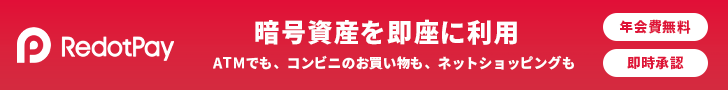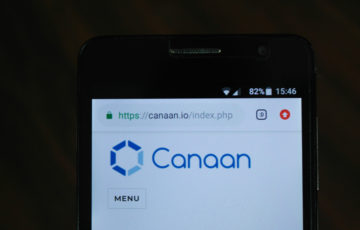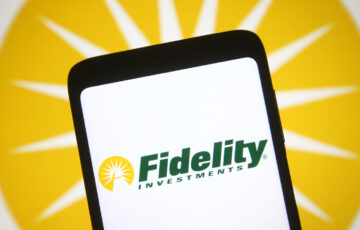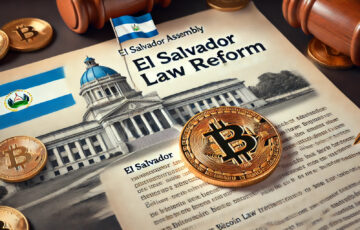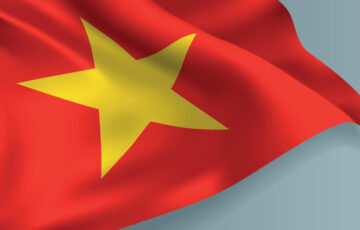金融庁が仮想通貨の監督強化を模索
金融庁は、仮想通貨の監督を資金決済法からより厳格な金融商品取引法へ移管することを提案した。
金融庁は2025年9月2日(火曜日)に発表した報告書で、仮想通貨を資金決済法から金融商品取引法に移管し、規制の対象とすることを提言。金融商品取引法では、仮想通貨はデリバティブ取引の原資産として使用される際に既に金融商品として扱われており、金融商品取引法を全面的に適用することで、仮想通貨の発行者に対し、公募および売出しに関する開示義務が課される。金融庁は、これにより「発行者と投資家間の情報非対称性が解消される」と主張している。
現在資金決済法の規制下にある仮想通貨は、金融商品取引法の下でより厳格な要件に直面することになる。金融庁は、仮想通貨に関する多くの問題は従来金融商品取引法で扱われてきた問題と類似しているため、同様のメカニズムと執行を適用することが適切な可能性があると主張している。
この移行は、デジタル資産の取引に関連する情報開示、価格変動、信頼性、リスクに関するより厳格な規則の施行を目的としている。
金融庁が挙げる仮想通貨投資への主な問題点
報告書で指摘されている仮想通貨投資の主な問題には、不明確なホワイトペーパー、不正確な情報開示、無登録取引、投資詐欺、低いリスク許容度、取引所におけるセキュリティ上の懸念などが含まれている。
ただし、同報告書は法的拘束力を持つものではなく、あくまでも金融審議会に意見を提出するために金融庁事務局が作成した内部説明資料である。審議会は金融担当大臣の正式な諮問機関であり、政府はこれを受けて新たな規則が必要かどうかを決定する。なお、提案された法改正案は、発効前に国会で可決される必要があり、可決されれば、規制の重複を避けるため、資金決済法は仮想通貨を監督しなくなる。
進化する日本の仮想通貨事情
日本国内における仮想通貨の開発は加速しており、今年(2025年)8月、加藤勝信財務大臣は、このセクターのリスクと可能性の両方を認め、デジタル資産はボラティリティが高いにもかかわらず、「分散投資の現実的な選択肢」であると述べた。
報告書は、日本経済において仮想通貨がますます重要な役割を果たしており、国内の仮想通貨取引所に開設された口座数は1,200万口座を超え、利用者の預金残高は5兆円を超えた。これは、ほぼ10人に1つの仮想通貨取引所口座がある計算だ。
大臣直属の金融審議会も、仮想通貨税制改革を推進している。当NEXTMONEYの2025年8月25日付特集記事「金融庁、仮想通貨税20%導入の大胆な仮想通貨税制改革を推進」で報じたように、仮想通貨税を新たなカテゴリーに分類し、2026年度の財政改革を前に20%の税率を、最大55%まで引き上げる可能性も示唆。また、今年後半に初の円建てステーブルコインの承認に向けて準備を進めており、発行者は、このステーブルコインの時価総額が1兆円に達すると予測している。
日本の規制強化の動きは、アジアにおけるより広範な傾向に沿ったもので、香港などの国々も、金融システムにおける仮想通貨の役割が拡大するにつれ、仮想通貨への監督を強化している。