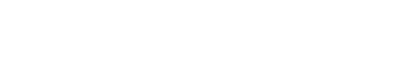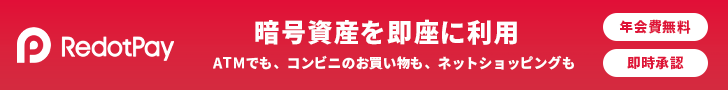カルダノ創業者がFRSを汚職で告発
カルダノ(Cardano/ADA)創業者であるチャールズ・ホスキンソン(Charles Hoskinson)氏は、FRS(Federal Reserve Banks:連邦準備銀行)が金融機関に対して差別的な行動を取ったことを受けて、汚職で告発した事がわかった。
同氏は、FRSが最近金融機関に対して差別的な行動を取ったことを受けての告発である。さらに、Custodia Bank(カストディア銀行)のケイトリン・ロング(Caitlin Long)CEO(最高経営責任者)が台頭したことで、事態は深刻化。また、ホスキンソン氏は、2024年の選挙で「仮想通貨に投票する」よう国民に呼びかけ、次のようにツイートしている。
Remember in 2024 to vote crypto, or else you get more of this corruption https://t.co/sPJ1I5j6kW
— Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) May 22, 2024
2024年には仮想通貨に投票することを忘れないでください。そうしないと、この腐敗がさらに増えます。
カストディア銀行CEOの発言がカルダ祖創設者に激しい怒りをかき立てる
FRSの差別的行為とされる行為に公然と反対してきたロング氏による激しい投稿は、カルダノ創設者の怒りをかき立てる形となった。
🚨SCOOP: Connecticut-based fintech bank Numisma (formerly named Currency Reserve) has received conditional approval for access to a Federal Reserve master account, making it the second non-FDIC-insured, non-federally regulated bank to receive one in recent years.
What’s…
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) May 21, 2024
スクープ:コネチカット州に拠点を置くフィンテック銀行Numisma(旧称Currency Reserve)は、連邦準備銀行のマスターアカウントへのアクセスについて条件付き承認を受けており、これにより同社は近年、FDICの保険に加入しておらず、連邦規制も受けていない銀行として2番目にマスターアカウントへのアクセスを承認されたことになる。
ここで注目…
ロング氏の批判は、連邦準備制度が元連邦準備制度当局者とつながりのある一部の銀行に優遇措置を与えていると同氏が認識していることにも焦点を当てており、ロング氏は「私は静かにしている」と主張。FRSの監察官がマスターアカウント手続きの調査を「一時停止」してから数週間後、これがまた別の元収容者に対する優遇措置のように見えるのだろうか。フォックスのジャーナリストであるエレノア・テレット(Eleanor Terrett)氏は最近、この話題をさらに煽る調査結果を発表。テレット氏は、コネチカット州に拠点を置くフィンテック銀行のNumisma Bank(ヌミスマバンク、※旧名:Currency Reserve[カレンシー・リザーブ])が、連邦準備銀行のマスターアカウントへのアクセスを条件付きで承認されたことを明らかにした。
Numisma BankはCustodia Bankと同様、連邦規制もFDIC(Federal Deposit Insurance Corporation:連邦預金保険公社)の保険も受けていない銀行であるため、これは注目に値する。とはいえ、FRSは以前、これらの機関は本質的に安全でなく、不健全であると主張していたため、Numisma Bankの承認は意外と捉えられている。
テレット氏は、非難にさらなる勢いを与えている重要な側面を強調。同記者は続けて、「承認された銀行は両方とも、元FRSの職員とつながりがある」と指摘。その発言を裏付けるように、元FRS副議長のランディ・クオールズ(Randy Quarles)氏はNumisma Bankの創設者の一人である。2018年、もう1つの銀行であるReserve Trust(リザーブ・トラスト)がマスターアカウントを取得し、元FRS副議長のサラ・ブルーム・ラスキン(Sarah Bloom Raskin)氏を取締役会に加えている。
しかし、Kansas City Fed(カンザスシティ連銀)はその後、2022年にReserve Trustのマスター口座を解約。ロング氏はまた、二重基準と思われる点も強調。Custodia BankのCEOは次のように語っている。
連銀のカストディア拒否命令は、これらの問題がなぜ解決不可能なのかについて非常に詳細な説明を提供したが、今や同じ規制構造を持つ銀行が連銀から許可を受け、元連銀総裁が関与している。
XRP擁護派のジョン・ディートン弁護士が論争に加わる
さらに、リップル(Ripple/XRP)支持派のジョン・ディートン(John Deaton)弁護士は、FRB(米国連邦準備制度理事会)に対して汚職容疑を申し立てる高まる批判の声に加わった。
ケイトリン・ロング氏とチャールズ・ホスキンソン氏による最近の告発に応えて、同弁護士はソーシャルメディアを利用し、連邦規制機関の客観性に対する疑念を表明したうえで、次のように断言している。
何度も言ってきたように、私たちは歴史書が後に「腐敗の時代」と記すであろう時代を生きています。