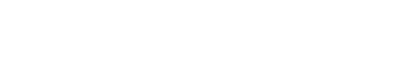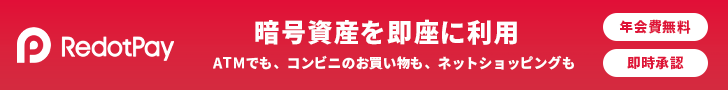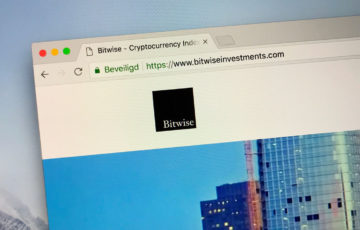仮想通貨市場回復の中、Lidoが持続可能な成長へ向けた構造改革
イーサリアム(Ethereum)最大の流動性ステーキングプロトコルであるLido(リド)は、運営コストの最適化と事業集中を目的に、全体の約15%にあたる従業員を削減した。
As part of efforts to ensure long-term sustainability, Lido Labs, Lido Ecosystem, and Lido Alliance have made the hard decision to reduce the size of their contributor teams, impacting around 15% of the workforce.
This decision was about costs — not performance. It affects…
— Vasiliy Shapovalov (@_vshapovalov) August 1, 2025
Lido Labs、Lido Ecosystem、Lido Allianceは、長期的な持続可能性を確保するための取り組みの一環として、コントリビューターチームの規模を縮小するという苦渋の決断を下しました。これにより、従業員の約15%に影響が出ます。この決定は…
この措置は、Lido LabsやLido Allianceをはじめとするエコシステム全体の貢献者に影響を与えており、プロジェクト全体の効率化と集中戦略を反映したものとなっている。
組織のスリム化と注力領域の明確化
Lidoの共同創設者であるヴァシリー・シャポバロフ氏は、「この決定はパフォーマンスではなくコストを考慮したものであり、LDOトークン保有者の長期的利益に資する重要分野にリソースを集中させる」と説明し、「困難な判断ではあったが、長期的な持続可能性のために不可欠だった」とも述べている。
Lidoは2020年に設立され、今回が初の人員削減となる。DAOによって運営されており、複数のブロックチェーン上でステーキング基盤を提供している。多くの貢献者は独立しており、サービスプロバイダー経由で活動している。
ガバナンスと分散化の強化
DAOは第三者監査を受ける体制を整えており、セキュリティ面でも一定の信頼性を保っている。LDOはガバナンストークンとして機能し、保有者は重要な意思決定に投票できる。
最近ではデュアルガバナンスモデルが導入され、stETH保有者が提案を最大45日間延期できる制度が新設された。これは分散化と安全性をさらに高める仕組みとされている。
回復基調のDeFi市場とLidoの戦略
Lidoはステーキング分野で圧倒的な存在感を持ち、イーサリアム上のTVL(総ロック資産額)は310~320億ドル(4.58兆円~4.72兆円)に達している。
2位のバイナンス(Binance)と比べて3倍以上の規模で、イーサリアムベースのLST(リキッドステーキングトークン)市場でもシェアは60%を超える。Lidoが最近展開を開始した「Lido v3」では、モジュール型アーキテクチャとstVaultsを導入。ユーザーはネットワークやバリデータセットへのエクスポージャーを柔軟に調整できる設計となった。
市場圧力と財務基盤の現状
シャポバロフ氏は、プロトコル開発やバリデータの分散化、研究領域への投資を今後さらに強化すると述べている。
DeFiLlamaによると、Lido DAOの年間収益は約9,000万ドル(約133億円)に達する見込みで、財務体質は引き続き健全とされる。また、Lidoの中核貢献者の給与は約800万ドル(約11.8億円)、運営費も同程度とされる中、今年現在での収益は既に4,000万ドル(約59億円)を超えている。ガバナンスや財務面の改革を進めながら、ユーザーサービスやプロトコルの安定性への影響を回避する方針を示している。
一方で批評家は、過去の急成長に伴うガバナンス面の課題が積み残されていると指摘し、今回の整理が遅きに失した対応と見る声もある。また、年初にはバリデーターパートナーであるChorus Oneとの間でトラブルが発生し、DAO内部の緊張感が表面化した経緯もある。
他プロジェクトの動向との対比
同じくDeFi(分散型金融)分野で存在感を持つCurve Financeでは、L2(レイヤー2)ネットワークの開発方針を見直す動きが出ている。
DAOに提出された提案では、手数料収益が限られる中でのL2統合作業を停止すべきという意見が出されている。CurveのTVLは約22億ドル(約3,250億円)で、取引量の大半がイーサリアムメインネット上に集中しており、現在は本体ネットワークへの依存が強まっている。
今回のリドの再編は、2022~2023年の過熱した成長期を経たDeFi業界全体が、持続可能な運営モデルへの移行を進める中での一手といえる。