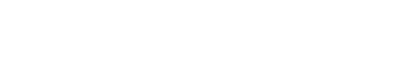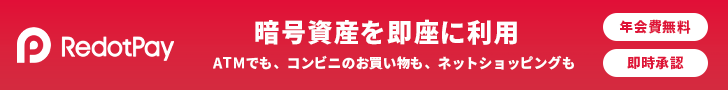11月7日に行われたCREATIVE SPORTS LAB TALK EVENT 009 「地域通貨の可能性を探る」という横浜DeNAベイスターズ主催のイベントに参加しました。
そもそも地域通貨とは特定の地域のみで扱われる通貨であり、仮想通貨とは異なる通貨です。今回の地域通貨は円にペッグした形で作成されるようです。横浜で地域通貨を発行するためにどのような取り組みをしていくかについて説明がありました。また、実際に通貨を使用して購買体験も行われました。
インタビュー動画 & スケジュール
- CREATIVE SPORTS LAB(THE BAYS 2F)のご紹介
- 「地域通貨」について基調トーク
- ブールバードカフェ「&9」での電子地域通貨のユーザーシーン体験
- ディスカッション
CREATIVE SPORTS LAB(THE BAYS 2F)のご紹介

引用元:THE BAYS公式サイトより
まずは施設紹介が行われました。
横浜DeNAベイスターズの提唱する横浜スポーツタウン構想のパイロットプログラムとして、新たな取り組みを発信する拠点「THE BAYS」は、Sports x Creativeをテーマとして、新たなライフスタイルや産業を生み出していくことで、日本大通り地区や横浜のまち全体に賑わいを創り出すことを目的としています。
CREATIVE SPORTS LABは、横浜DeNAベイスターズが運営する会員制シェアオフィス&コワーキングスペースであり、さまざまな用途で使用できるとてもおしゃれな空間でした。
また、1FにはLIFETIMEにBASEBALLをプラスするLifestyle shop +B、こだわり抜いた球団オリジナル醸造ビールで球場内と同じビールがいただけるBoulevard Cafa &9があり、B1にはスタジオ/アウトドア フィットネスプログラムACTIVE STYLE CLUBがあります。
「地域通貨」について基調トーク

- 日本政策投資銀行 地域企画部 課長 坂本 広顕氏
基調トークとしてDBJ(日本政策投資銀行)坂本氏が、地域通貨の可能性と地域の自立活性化について述べられました。
坂本氏は、地域における企業への融資業務や、企画・調査業務などに従事し、Fintechを活用した地方創生を貨幣研究やeスポーツ調査と合わせてライフワークとして楽しみながら進めておられます。
稼げる地域になるためには、お金の地産地消が大切であり、現在の地域経済構造は、バケツに穴が空いている状態であるとの見解を示しました。また、地域で8割の消費をすると消費した金額の5倍の価値(経済効果)があります。
貨幣の機能「価値尺度」「決済性」「価値貯蔵」
貨幣の機能は「価値尺度」「決済性」「価値貯蔵」の3つからなり、法定通貨にはそれが備わっています。仮想通貨の場合は、ボラティリティが高く「価値尺度」「決済性」に問題がある場合が多く、貨幣としての機能を果たしていません。電子マネーの場合は、全国的に使用ができ、地域のお金がエリア外に流出してしまいます。
地域通貨の場合、このような問題点を解決することが可能であり、
- 価値尺度:円にペッグしているため安定。
- 決済性:エリア内のみ可能であり、限定的であるため、地域外に流出しにくい。
- 価値貯蔵:一定期間のみであり、決済性がエリア内に限定されるため、消費に回りやすく地産地消を促進することができる。
また、次の3つの中での循環を、どのように効率よく循環させていくかが大切であると述べられました。現代版の藩札のような形をイメージしているとのことです。
- 発行、運営事業者
- 加盟店
- 顧客
当初の課題としては、2つ挙げられます。
1つは加盟店の確保です。どのように加盟店に優位性を持たせ、増加させていくかが課題として挙げられます。全国的なFC(フランチャイズ)店舗を地域限定で決済可能にすることや商店街の店舗を最低800店舗は始める段階で必要になると述べており、地域全体を巻き込む必要があります。
2つ目は、満足度への配慮です。円にペッグしているため投資商品ではありません。よって、ユーザーに対してどのようなメリットを作るべきかというところが課題となります。
予定として、ポイント制、換価時のプレミアム性、仮想通貨等への両替が検討されています。
実際に電子版地域通貨の発行事例として、2017年12月より飛騨信用組合が「さるぼぼコイン」、2016年10月より崎県離島エリアでは「しまとく通貨」が発行されており、法定通貨を使用するより、さまざまな優位性があります。
ブールバードカフェ「&9」での電子地域通貨のユーザーシーン体験
1Fのブールバードカフェ「&9」で購買体験が行われました。
実際にベイスターズコインを使用して、コーヒーやビールなどを購入する体験であり、とても利便性が高い印象でした。

ディスカッション

- 日本政策投資銀行 地域企画部 課長 坂本広顕氏
- 処デザイン学舎代表 慶応義塾大学SFC研究上席所員 斎藤美和子氏
- 長崎県市町村総合事務組合 しま共通地域通貨発行委員会 久保雄策氏
最後にこの3人によるディスカッションが行われました。
テーマは「地域通貨」が成功するキーは?というテーマで質問形式で行われました。その中で回答を要約します。
現金を使わない日はありますか?
三者ともにキャッシュレスで増えてきていると答え、3年ほど前までは考えられなかった。
今、便利だと思う決済手段は?
Nanaco、Suica、クレジットカードなどが挙げられました。その中で、どのような優位性があるかということと、使用可能店舗が多いことが判断基準であり、地域通貨を発行する際もこのようなことを考慮する必要があります。
「地域」を区切ることってどういう意味があります?
メリットとしては、地産地消が可能となり、資金の流出を防ぐことができる点。そして、情報提供を適切に行えるため、住民の理解を得るために必要であり、地域の境界は人それぞれ異なるため、しっかりと区切ることでコミュニティができる点が挙げられました。
一方デメリットは、地域で区切ると加盟店の壁がある点が挙げられました。
ターゲットユーザーはどこに置きますか?
どこかに絞るということはなく、BtoB、BtoCの資金循環の中でリンクするところがターゲットなるとのことでした。
他との差別化、どのようなバリューを求めますか?
地域通貨はあくまで道具であり、地域の特性をどう生かせるか、決済手段だけでなく、ゲームを導入して楽しさとしてのバリューを出しても面白いということでした。
地域通貨に対する考察・まとめ
このような仮想通貨は違った形の通貨もキャッシュレスとなっている日本では、今後台頭してくると感じました。
地域密着型の通貨であり、地域の資金流出を防ぐため、地域の活性化には欠かせないものとなるでしょう。また、横浜市では横浜DeNAベイスターズというプロ野球チームや横浜中華街も存在するので、マーケティングもしやすく、早い段階での定着が期待できると感じました。