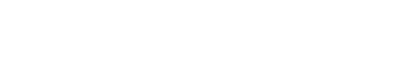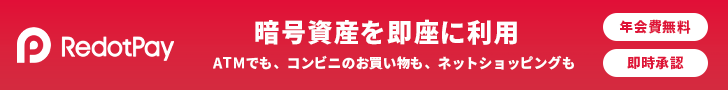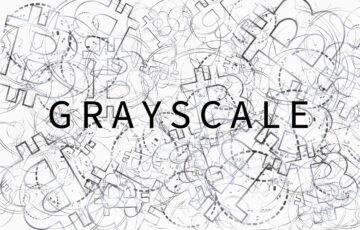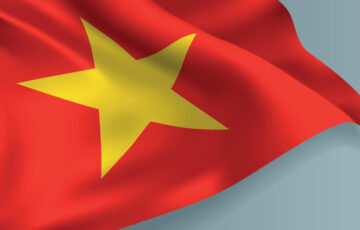故ジョン・マカフィーの妻がミームコイン「AIntivirus(AINTI)」をローンチ
未亡人となった故ジョン・マカフィー(John McAfee)氏の妻ジャニス-エリザベス・マカフィー(Janice-Elizabeth McAfee)氏がミームコインを立ち上げ、トークン配布をめぐる議論を巻き起こしている。
Ever since John's untimely death, I have been looking for ways to honour the genius he was and build on the legacy he left behind.
I am super excited to announce that I have taken creative control of a product that will expand John's legacy. It encompasses his core beliefs of… pic.twitter.com/P7Ir932b3E
— Janice Elizabeth McAfee (@theemrsmcafee) January 23, 2025
ジョンが早すぎる死を迎えて以来、私は彼の天才性をたたえ、彼が残した遺産をさらに発展させる方法を模索してきました。
私は、ジョンの遺産を拡大する製品のクリエイティブなコントロールを引き継いだことを発表できることを非常に嬉しく思っています。この製品は、ジョンの核となる信念である自由、プライバシー、テクノロジーを包含し、暗号とAIに対する彼の情熱を拡大するものです。
ジョンは仮想通貨のこのサイクルを気に入っていただろうし、彼が死後も参加できるプロジェクトを見つけることができて私はうれしい。
ジョン・マカフィー氏の妻であるジャニス氏は、亡き夫の功績をたたえるために、AI(人工知能)をテーマにした新しいミームコイン、「AIntivirus(AINTI)」を立ち上げた。AINTIは夫の功績をたたえるために作られたと主張しているが、オンチェーンアナリストは、このプロジェクトで内部者の活動が活発であることを発見し、トークンの供給について懸念を表明する者も多い。
Solscan(ソルスキャン)の調査によると、トークンの大部分は、プロジェクトの内部関係者の所有物と思われる多くのウォレットに移動。この取り組みの背後にいるチームのメンバーを豊かにすることに重点が置かれている可能性が高いことが示唆されている。
AIntivirus(AINTI)ローンチが物議を醸す
ジャニス氏は、Xへの投稿で、ジョン氏の突然の死後、夫をたたえ、彼が残した遺産を活かす方法を模索していたことを明らかにした。
2 度アメリカ大統領候補となったジャニス氏は、亡くなった夫はこの仮想通貨サイクルを気に入っていただろうし、夫が「死後参加」できるプロジェクトを見つけられて嬉しいと主張した。ジョン氏のXアカウントは、死後もまだ稼働しており、マカフィー自身のAIバージョンであるAINTIと呼ばれている。
ジャニス氏の投稿のコメント欄には、AIntivirus のローンチについて物議を醸す意見を述べるコミュニティメンバーが溢れており、同氏が初めて「honor(=名誉)」を「honour」と綴ったため、アカウントがハッキングされたのではないかと推測する声も。ジョン・マカフィーのアカウント復活、あるいはミームコイン自体にまったく納得していない人もおり、カルダノブロックチェーンの作成者であるチャールズ・ホスキンソン(Charles Hoskinson)氏は、Xへのローンチ投稿に皮肉を込めて次のように反応している。
John being resurrected as a dubious AI crypto scam us the most John McAfee thing possible. It's going to develop a digital drug habit within a week and then start a metaverse called New Belize before escaping to Europe.
— Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) January 23, 2025
ジョンが怪しげなAI暗号詐欺として復活するのは、まさにジョン・マカフィーらしいことだ。1週間以内にデジタル麻薬中毒になり、ニューベリーズと呼ばれるメタバースを開始してからヨーロッパに逃げるだろう。
専門家による分析
オンチェーン専門家による分析では、トークンの供給と配布に問題があることが発覚。ブロックチェーンデータプラットフォームBubblemapsによる一連のツイートは、AINTIに関する大規模なインサイダー活動を明らかにしている。
Bubblemapsは、トークン配布業者VirUsがトークンが発売される前に、AIntivirusの総供給量1億の90%を287のアドレスに送信したことを発見。AINTIがリリースされるとすぐに、60のアドレスがウォレットを空にして150万ドル(約2.3億円)を受け取った。また、他のウォレットが供給量の71%を保有しており、発売前のこのコインの転送は、アドレスがプロジェクトの背後にあるチームのものであることを示唆している。
ジョン・マカフィー氏の遺産とストーリー
ジョン・マカフィー氏はサイバーセキュリティへの貢献で広く知られた人物だ。
ジョン氏の会社であるMcAfee Associates(マカフィーアソシエイツ)を通じて、複数のウイルス対策プログラムを作成およびリリースし、2021年にスペインの刑務所の独房で亡くなっているのが発見されるまで、人気の仮想通貨支持者であった。2020年、米国当局はジョン氏を脱税とICO(Initial coin offering:新規仮想通貨公開)の詐欺的宣伝で告発。同氏は同年にスペインで逮捕され、死亡する前に米国に引き渡される準備が整っていた。