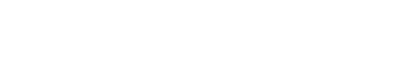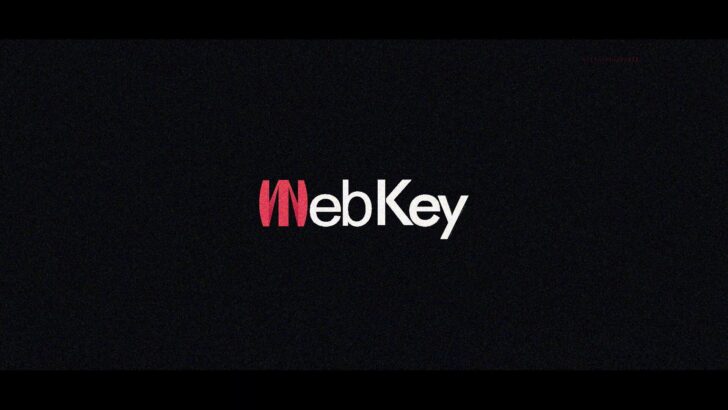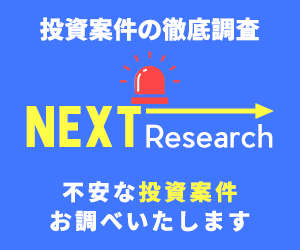「WebKey」投資案件の実態と信頼性──高利回りの裏に潜むリスクとは?
プロジェクトの概要
WebKey(ウェブキー)は、自称「次世代のインターネットインフラ」を目指す分散型プラットフォームです。ブロックチェーンを活用した分散型物理インフラネットワーク(DePIN)の構築を掲げ、150種類以上のブロックチェーンをシームレスにつなぐ新経済圏を実現すると謳っています。
Webkey公式URL:https://www.webkey-japan.com/
具体的には、スマートフォンなどのWeb3対応端末(WebKeyフォン)を通じて誰もがWeb3経済に参加できる環境を提供し、個人がインフラ構築に貢献して報酬を得られる仕組みを目指すとされています。公式情報によれば、WebKeyはアフリカ・東南アジア・南米など新興国市場でスマートフォン等の普及を図り、既存のWeb2アプリ(TwitterやTelegram等)とWeb3ツール(MetaMask等)をプリインストールした独自端末を展開中とのことです。

WebKeyのプロモーション画像の一例。スマートフォン端末と複数のブロックチェーン(Ethereum, BSC, Polygon, Solanaなど)対応を強調し、「This Time Let’s Redefine Web3(今こそWeb3を再定義しよう)」と謳っている。
このプロジェクトには独自トークン「WKEYDAO」が存在し、Binance Smart Chain(BSC)上で発行されています。WKEYDAOは2023年に発足したプロジェクトで、2024年11月7日にサービス開始。2025年春時点で公称 ウォレット開設数10万件を突破し、BSC上のプロジェクト評価ランキングでトップになったと宣伝されています。
またANUBI財団と称するWeb3特化のベンチャーキャピタルから1億ドル(約155億円)もの資金提供を受けたともPRしています。公式サイトでは
「多くのプロジェクトが参加者資金に頼る中、WebKeyは巨額の開発費で技術を完成させた」
と強調しており、参加者から集めたお金ではなく財団出資により開発が進んでいるとアピールしています。ただし、このANUBI財団による投資発表はBinanceの公式ニュースにて「DePIN領域の技術革新支援のため1億ドル規模ファンド設立」という一般論として報じられたのみで、WebKey個別への出資が明言されたわけではありません。
一方でANUBI財団側もSNS上でWebKeyへの支援を公言しており、例えば2024年秋に40万ドルの追加支援を行ったとも投稿されています(※ANUBI財団公式Xアカウントの投稿より)。
🌍💥 Anubi Foundation proudly supports WebKey’s Global Sprint Month!
With a $400K investment, we’re fueling WebKey’s growth and powering its global community. From Korea to Bali, we’re driving the Web3 revolution forward—#FullSpeedAhead for 2024, together toward a brilliant… pic.twitter.com/C1Qw0rVGXz
— Anubi (@Anubi_sab) December 2, 2024
このようにWebKeyは「強力な資金的後ろ盾がある」と演出しつつ、2025年までに30万台のWeb3スマートフォンを出荷予定とも豪語しています。
さらにAnimoca Brands、Binance Labs、TRON、OKXといった大手との提携もあるとプレスリリースで謳っています(※ただしこれら提携はプロジェクト側の主張であり独立した裏付けは確認できません)。
プロジェクトの収益モデルについて公式には明確な記載がありませんが、推察されるのは独自トークンの発行・流通とハードウェア(スマホ端末)の販売です。
ユーザーは後述する手順でUSDT(テザー)を預け入れることでWKEYDAOトークンを入手し、その保有量に応じて追加のトークン報酬を受け取ります。つまり一般参加者にとっては「USDTを預けてWKEYDAOを購入・ステーキングし、高利回りを得る」こと自体がインセンティブとなっています。
このため現状、プロジェクトの主たる収益源はスマホ等の実需よりも新規参加者からの資金流入、およびトークン価格上昇に伴う含み益と考えられ、いわゆる投資スキーム色が強い構造と言えます。
運営会社の実態(登記情報・所在地・代表者等)
WebKeyプロジェクトの運営主体は極めて不透明です。公式サイトには会社概要や運営法人の情報が一切掲載されていません。日本語サイトの「運営者情報」ページには「本ページはWebKey日本チームのリーダー有志によって運営しています」と記載があるのみで、企業名や所在地、責任者氏名等の基本情報が伏せられています。

このことから少なくとも日本国内に「WebKey」という商号で登記された会社は存在しないか、存在しても一般に公開されていない可能性が高いです。実際、国内の法人登記・商標データベースを調査しても「WebKey」名義の新規法人設立記録は見当たりません。(過去に無関係の会社が取得していた商標登録は確認できますが、現在のプロジェクトとは無関係とみられます)
運営母体として度々名前が出るANUBI財団についても、その実体ははっきりしません。海外発のWeb3投資ファンドとうたわれていますが、本拠地や代表者など詳細は不明です。
財団の公式X(旧Twitter)アカウントは存在しWebKey支援に言及していますが、法人的な所在は開示されていません。
また、Xへの投稿内容のほとんどが企業理念のようなものと、WebKey関連の投稿のみとなっており、その実態が定かではありません。
WebKey日本チーム以外にも各国ごとにコミュニティ組織(例:「WebKey India」等)があるようですが、あくまで「有志チーム」の体裁であり正式な支社や現地法人ではない可能性があります。
要するにWebKeyは特定の企業よりも、実体不明の財団やコミュニティ主導で展開されているプロジェクトであり、参加者にとって運営者の実態を把握しづらい状況です。これは金融商品を扱う事業としては異例であり、信頼性を判断する上で大きな不安要素となります。
報酬体系や仕組み(投資リターン構造・紹介制度など)
投資リターン構造
WebKeyの報酬体系は高利回りのトークン配当と紹介ボーナスを特徴としています。
まず基本となるのはステーキング報酬による高配当です。公式マニュアルによれば、ユーザーは専用ウォレット(推奨はTP Wallet)を用意し、BSC(BEP20)規格のUSDTを入金した上でWebKeyの招待リンクからアカウント登録します。
登録後、WebKeyシステム内でUSDTをWKEYDAOトークンにスワップ(交換)購入し、そのまま自動でステーキング(預け入れ運用)を開始する流れになります。ステーキングを開始すると12時間ごとに0.4%(1日あたり約0.8%)の割合で報酬が発生し、得られた報酬はWKEYDAOトークンとしてアカウントに加算されていきます。この0.8%/日の利率は固定ではなく多少の変動があるとされていますが、公式資料の例示では概ね年利ベースで数十倍(後述)という驚くべき高利回りが提示されています。
報酬の仕組みを理解する鍵は、WKEYDAOトークンの発行メカニズムです。
WebKeyでは典型的なDeFi案件のように事前に大量のトークンを発行せず、ユーザーが参加のためUSDTを投入したときに初めて対応するトークンを生成する「オンデマンド発行」を採用しています。
ルール上、1 USDTの参加につき1 WKEYDAOが新規発行される仕組みで、例えば500ドル分のUSDTを入れた場合には500 WKEYDAOが新たに発行されます。しかしその時点でユーザーが市場から実際に得られるトークン数は、USDT投入額を現在の市場価格で割った量のみです。
仮に市場価格が1WKEYDAO=$50であれば、500ドルでは10 WKEYDAOしか購入できません。残りの490トークン(500発行-10取得)はユーザーに即時付与されず、システム内にプールされます。
このプールされたトークンこそが、今後ユーザーへのステーキング報酬として分配されていく原資となります。
上述の利率0.8%/日で言えば、最初に取得した10 WKEYDAOに対し1日あたり0.08 WKEYDAO(=10×0.8%)が配られ、元々プールされていた490個から徐々に差し引かれていきます。
単純計算で490 ÷ 0.08 ≈ 6,125日、約16.8年間はこのペースで報酬支払いが可能だという理屈になります。
公式はこの試算を示し「十分無理なく正当な配布が行える」と主張しています。もっとも、この算出はトークン価格が高値で安定し続けることを前提にしています。価格が大きく変動すれば発行・配布バランスも変わり、実際に何年も高利回りが維持できる保証はありません。
紹介制度
次に紹介制度(アフィリエイト制度)ですが、WebKeyは完全招待制を採っています。
新規参加には既存ユーザーから提供される招待リンクが必要であり、誰かの紹介なしには始められません。この仕組みはマルチレベルマーケティング(MLM)的な要素を持ち、紹介者には一定の報酬が入るとみられます。
具体的な紹介ボーナス率や階層について公式サイト上では明示されていないものの、SNS上の情報や類似案件の例から推測すると直紹介の入金額に対する○%のコミッションや、さらに下位層の紹介活動に応じた段階的ボーナスが設定されている可能性があります。
中国の情報源によれば「チームを発展させれば静的収益(月利43%程度)より高い動的収益が得られる」とされており、単に預けるだけの利益だけでなく下線(ダウンライン)構築による追加収入が用意されていることが示唆されています。
実際、国内外のSNS上でも積極的に新規参加者を勧誘する投稿が散見され、「12時間ごとに0.4%の利益」「1年後には複利で元本の18倍になる」等と高配当と紹介メリットを強調した宣伝が行われています。
以上より、WebKeyの収益構造は参加者自身の出資に対するトークン配当(高利率)と新規参加者紹介によるコミッションの二本立てであり、典型的なHYIP(高利回り投資案件)やポンジ・スキームに類似した形態となっています。
出金(利確)
ユーザーが得たWKEYDAO報酬を出金(利確)する手順も独特です。
マニュアルによれば、出金申請を行うとシステムが自動的にWKEYDAOをUSDTに売却し、そのUSDTが即座にユーザーのウォレットに送金される流れです。但し実際には「出金されたWKEYDAOは12時間ロックされ、その後ボタン操作でウォレットに移動可能」という時間差や、利益額に応じて0~15%の手数料(俗に“酒造税”と称される)が差し引かれるなどの条件が付与されています。
この手数料は条件次第で0%にもできるとありますが詳細不明です。
一般にこの種の投資スキームでは、早期の利確にはペナルティ課税して再投資を促す狙いがあるため、WebKeyでも大口の利益引出し抑制や長期運用奨励の仕組みと思われます。
金融庁への登録状況や法的届け出
WebKeyは日本の金融当局への登録を一切行っていないと考えられます。
まず、本プロジェクトは暗号資産(仮想通貨)を扱いますが、金融庁に登録された暗号資産交換業者の一覧に「WebKey」あるいは運営母体とされる名称は見当たりません。
また、有価証券や預り金を募る行為にも該当し得ますが、金融商品取引業者や第二種金融商品取引業等の登録も確認できません。金融庁が公表している無登録業者リスト(無登録で金融商品取引業等を行う者の名称一覧)にも2025年5月時点でWebKeyの記載はなく、まだ当局の注意喚起対象となっていないか、名称を変えて活動している可能性があります。
もっとも、現在WebKeyが採っている手法は「ユーザー自身がDEX/ウォレットを用いて自己責任でトークンスワップ・運用する」という体裁であるため、一見すると運営側が直接出資金を集めている形ではないようにも見えます。このような場合、法律上のグレーゾーンを突いて無登録のまま活動しているケースも散見されます。
しかし実質的にはWebKey運営側が利回り保証を示唆して資金集募を煽っている点で金融商品取引法や出資法等に抵触する恐れが指摘できます。
特に、日本在住者を勧誘している場合、出資の受入れ・元本超過配当の約束は無限連鎖講(ねずみ講)防止法にも抵触しかねません。また「債券購入」という文言もマニュアル内に登場しますが、仮に債券的な商品性をうたうのであれば有価証券の無許可募集となり違法です。現状、公的機関からWebKeyに対する個別の行政処分や警告は出ていません。
しかしこれはプロジェクトが始まったばかりで認知が低いためか、あるいは当局の目をかいくぐっているだけとも考えられます。いずれにせよ日本の法律に基づく正式な登録・届出がない時点で、WebKeyへの出資勧誘は違法性を帯びる可能性があり、利用者保護の枠外でリスクを負うことになります。
SNS・掲示板・ブログ等での評判や口コミ
WebKeyの評判はSNS上で二極化しています。
一方では紹介者(アフィリエイター)と思われる人物らが「驚異的な利益が出た」「毎日利息が増えて夢のようだ」といった成功談を拡散し、新規勧誘に熱心です。
X(旧Twitter)上には「12時間ごとに0.4%のリターンが得られ、複利運用で1年後には元本の18倍に増える」「世界で10万アカウント達成」などと高収益性を強調する宣伝ツイートが複数確認できます。またYouTubeやTelegramなどでも「稼げるWeb3スマホ」としてWebKeyを紹介するコンテンツが投稿されており、プロジェクト参加を促す動きがあります。こうした発信にはしばしば招待リンクや連絡先(LINEオープンチャット等)が添付されており、紹介マーケティングの一環とみられます。
他方、WebKeyを疑問視・批判する声も少なくありません。
日本語圏ではまだ情報が限られるものの、匿名掲示板やTwitter上で「典型的なポンジスキームではないか」「利率が不自然に高すぎる」「会社実態が見えず怪しい」といった指摘が出ています。
特に暗号資産界隈で詐欺案件を追跡するユーザーからは、WebKeyの報酬プランが過去のポンジ案件と酷似しているとして警戒が示されています。
LINEオープンチャットでは「WebKey倶楽部」と称するコミュニティが存在しますが、その説明文には「主に詐欺撲滅・ポンジ・スキームは厳禁…合法的な将来を生暖かく育てていくコミュニティー」といった記述があり、真偽不明ながらWebKeyを擁護する一方で詐欺との関わりを否定したい意図もうかがえます。
総じてSNS上では、勧誘側はひたすらメリットを強調し、中立的な第三者や有識者は強い懐疑的見解を示している状況です。日本の一般投資家向けブログや大手メディアでの取り上げはまだ少ないものの、このまま拡散すれば「高配当を謳う怪しい投資話」として注意喚起される可能性も高いでしょう。
ポンジ・スキームや詐欺との関連指摘
インターネット上ではWebKeyがポンジ・スキーム(いわゆるねずみ講的詐欺)ではないかとの指摘が数多く見られます。
その理由は、先述した極端に高い利回り(年利数千%級)と新規参加者の紹介奨励という典型的特徴を備えているためです。
中国の反詐欺コミュニティ「李旭反传销团队」は2024年末にWebKeyを取り上げ、「11月に登場した空気币(実体のない暗号コイン)が資金盤(ポンジ)を大々的にやっている。公開透明・グローバル機関認証済みとうたい、スマホでマイニングして静的収益は月利43%、年複利で27~79倍になると宣伝、さらにチームを発展させれば収益がもっと上がる。このモデルは伝销(マルチ商法)や違法集資の疑いがある」と警告しています。実際、年複利27~79倍という数字は前述の0.8%/日複利運用による約18倍を上回っており、紹介報酬等の「動的収益」を加味した誇張と考えられますが、いずれにせよ常識外れの高配当であることに変わりはありません。
また、WebKey DAOトークン自体の不自然さも詐欺を疑われる一因です。
WKEYDAOの価格は2024年末から急騰し、一時50ドル近辺に達しました。その結果、発行済み枚数約266万枚で時価総額1億ドル(百数十億円)規模に相当する計算になります。
しかしこの価格は運営が提供する自前の流動性プールや限られたDEX上の出来高によって維持されているとみられ、市場参加者による正当な評価とは言い難い側面があります。運営が意図的に価格を維持・吊り上げ、それによって参加者に「含み益が出ている」「トークンが値上がりしている」と思わせることで更なる資金流入を促す手口は、過去のポンジ型暗号資産でも度々指摘されました。
WebKeyでも、巨額の「恒久的流動性サポート」を行ったとニュースで喧伝していますが、これは運営または関係者がマーケットメイクをして価格維持を図っていることの裏返しとも取れます。
実際、ブロックチェーン分析企業GoPlus Securityは「WebKey DAOのコントラクトは発行可能上限が大きく、開発者がいつでも大量の新規トークンを発行できる。ユーザー保有分が大幅に希薄化する恐れがある」と技術的リスクを指摘しています。
要するに、運営側の裁量でいくらでもトークン供給を増やせる=配当原資を“印刷”できる状態であり、これは典型的なポンジスキームの構造(後から参加した人の拠出で先行者に配当を払う)と軌を一にします。
さらに、WebKeyは表向き「画期的なWeb3インフラ事業」としていますが、少なくとも現段階でその事業成果や収益源となるプロダクトが十分確認できません。宣伝されているWeb3スマートフォンも実物の一般販売や詳細スペックの公開がなく、300,000台出荷という目標も現実性に疑問符がつきます。プロジェクト開始から半年あまりで世界中に10万ユーザーという触れ込みも実態不明であり、ユーザー数・コミュニティ規模の誇張も詐欺スキームではありがちな手法です。
総合すると、WebKeyは高配当をエサに出資金を集めるポンジ・スキームの疑いが極めて濃厚であり、各所でその点を警戒・批判する声が上がっている状況です。
第三者による評価・監査・注意喚起の有無
現時点で公的機関や信頼できる専門機関による公式な評価・監査報告は確認できません。
しかし、いくつかの第三者が注意喚起的な情報を発信しています。
前述のブロックチェーンセキュリティ企業GoPlus Securityは、BNBチェーン上のプロジェクト安全性分析の中でWebKey DAOを名指しし、「高リスク警告」を付与しました。
これは技術的なコントラクト面の脆弱性や不透明性に基づく評価ですが、投資リスクの高さを示す一材料と言えます。
また海外の詐欺チェッカーサイトであるScamadviserでも、WebKeyの関連サイト(app.webkey.vip)に対して「信頼スコアが低く、詐欺の可能性がある」との判定が出ています。同サイトでは運営者情報をWHOISで隠している点や、ドメイン開設から日が浅い点、利用者のレビューで低評価が付いている点などをマイナス要因として挙げており、客観的に見て信用できないウェブサイトであると分析しています。
さらに、中国の大手ポータルサイト搜狐网に掲載された記事では、WebKeyが他の疑わしい投資案件とともに「伝销・詐欺の可能性あり」と紹介されており(李旭反詐欺チーム提供の情報)、2025年2月時点で既に海外では被害拡大を懸念する声が上がっていることが窺えます。
同様に、香港発の暗号資産ニュースサイトでも「WebKeyは高リスク」「NVB Bankと並び注意」等と伝えられており、業界内では警戒対象になりつつあります。
日本国内ではまだ消費者庁や金融庁からの公式な注意喚起は出ていませんが、東京都や各県の消費生活センター等が発信する一般的な警告(SNS投資詐欺に注意など)に合致する事例と言えます。
今後、日本語でも被害報告が増えれば国民生活センターや警察による注意喚起が行われる可能性があります。現段階で第三者の積極的な評価・監査報告はないものの、民間レベルでは「高リスク・要警戒」との評価が下され始めているのが実情です。
総合評価・信憑性と詐欺リスクの分析
以上の情報を総合すると、WebKeyプロジェクトの信憑性は極めて低く、詐欺的リスクが高いと判断せざるを得ません。
公式の謳い文句は最先端の技術プロジェクトを装っていますが、肝心の収益モデルは新規資金に依存した高配当スキームであり、実態不明の組織が運営する点も典型的なHYIP型投資詐欺の特徴に合致します。特に「日利0.8%」「年利数十倍」「紹介で更にボーナス」といった約束は、金融商品の常識からかけ離れており、過去に無数に破綻してきたポンジ・スキームと軌を一にします。
実際、WebKeyは技術的にも無制限なトークン増発が可能であるなど不健全な設計が確認されており、仮に最初のうちは配当が支払われても、参加者が増え続けない限りいずれ維持不能に陥る蓋然性が高いです。
運営側が掲げる大型出資者(ANUBI財団)や提携先も、その信憑性には疑問符が付きます。1億ドルの投資話にしても、実態は一般論の転用でありプロジェクト自体への出資とは限りません。
提携先とされた有名企業も、それら企業から公式発表が無い以上プロジェクト側の一方的な宣伝とみるべきでしょう。要するに、権威付けや資金力を演出することで信用させようとしている可能性があります。さらに運営者情報を隠し、日本では無登録で活動していることから、何か問題が起きても責任追及や資金回収が極めて困難です。
口コミや第三者の見解も、冷静な分析ほど「危険である」と結論付けている状況です。高利回りに惹かれた一部参加者からは肯定的発言も見られますが、そうした声は往々にして紹介報酬目当ての可能性があり鵜呑みにできません。実際、中国では早くも警戒情報が出回っており、国際的には詐欺認定されつつあるような段階です。
総括すると、WebKeyは表向き先進的なWeb3プロジェクトを装いながら、その実態は未成熟な法制度の隙を突いた疑似投資案件と評価できます。現状で確認し得る公式情報・第三者分析のすべてが、同プロジェクトの不透明さとリスクの大きさを浮き彫りにしています。参加者は自己責任とはいえ、このような案件に資金を投じることは極めて危険であり、「投資」というより実質はギャンブルや詐欺に加担するリスクを伴うといっても過言ではありません。したがって、WebKeyに関しては慎重どころか近寄らないことが最善との結論に至りました。
参考文献・出典:
本調査レポートは公式サイトの記載、暗号資産専門ニュース、海外ポータル記事等の一次情報に基づき客観的に分析・評価したものです。各所に引用した出典を併せてご参照ください。